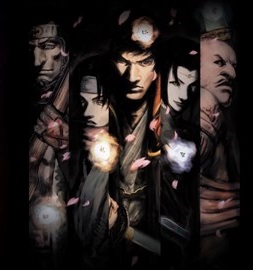今回は、『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』についての記事になります。
GBソフトの売り上げでは7位の記録で、235万本売れたという本作。

いまだに「神ゲー」として名が上げられ、モンスターズシリーズでも1番好きという人も多い本作はどんな作品だったのか?
当時キッズとしてプレイしていた僕が覚えていることを含めて書いていきますので見ていきましょう。

どんな作品だったのか?
配合のおもしろさ
本作はGBでは初めてのドラクエ作品でナンバリングとは違い、モンスターのみが戦う作品となっています。
今なお続くモンスターズシリーズの原点で、配合などの基本システムはこの頃から完成されていました。


モンスターが中心のゲームが作られた背景には当時社会現象を起こしていたポケモンの影響と言われています。

ポケモンはレベルが上がることで強さと見た目が変わるというものでしたが、本作は「配合」というシステムでその要素を取り入れています。
「配合」は当時のドラクエシリーズのプロデューサーが競馬好きだったということで、馬の種付けがヒントになって生まれた案とのこと。

当時はポケモンフォロアー作品が数多く出ていましたが、ほとんどはそこまでのヒットを生み出せずにいました。
そんな中で本作は「配合」によって差別化ができ、大きな売り上げを記録したのかもしれません。
この配合システムは「どんなモンスターができるんだろう?」という「試して探る」という楽しさがあったかと思います。

ドリンクバーで違う味をコップに入れてどんな味になるか試してみるとか子供の頃にやったああいう体験と似たような感覚がプレイ中にあったかと。

似たようなものではPSになりますが「モンスターファーム」もこういった感覚に近いものがあったかと思います。
CDを入れることでモンスターを生み出せるというシステムもまた「試して探る」ということがよくできていましたね。
もちろん売れたことはドラクエというコンテンツの強さが元々あったからというのもありますが「配合」というシステムはヒットした要素の1つかと思います。
ナンバリング作品の名シーン再現
またナンバリング作品の名シーンを再現していることもヒットの要因になったのかもしれません。

本作は「たびのとびら」という最下層にいるボスを倒すことが基本的な遊び方となっていますが、そのボスの多くがナンバリング作品の名シーン再現となっています。

これはシリーズファンへのサービスになっており、外伝作品には興味のないドラクエファンも購入するきっかけになったそうです。

堀井さんは当初魔王系モンスターが出てくることことに否定的だったということですが、「お祭りゲーとしてファンが喜んでくれるのならば」として受けいれたとのことです。
逆に本作でドラクエ関連の作品を初めて触った人も多いらしく、僕も本作がドラクエ関連作品初プレイのものでした。

そういった感じの子供が多かったからか、後に『1・2』『3』のリメイクがゲームボーイで発売という形になったようです。

まあその流れでプレイしたせいか、モンスターの能力値が基準になっていたため勇者の能力見ても「人間よえー」とか思ったことを覚えていますね(笑)

ちなみにリメイクの3DS版では魔王系のたびのとびらは廃止され、新たなストーリーに差し替えられています。
GB版との差別化を図るために新ストーリーを用意したのかもしれませんがこちらは不評だったようですね。
個人的にも発売当時に新ストーリーをプレイしましたが、まったく覚えていないんですよね。
なんかパッと出の輩どもが偉そうに何かしてた印象しかありません(笑)
これなら魔王系のボスと対戦させてほしかったですね。
当時の思い出やよく話題になること
グリズリーの圧倒的強さ
このゲームでよく語られていることと言えばグリズリーの圧倒的な強さ。

攻撃力の伸びがものすごく、無双するというやつ。
獣系×悪魔系という基本配合から生まれるキャラでありながら、攻撃力上昇値が全モンスター中3位というヤバさ。
序盤の同レベルのモンスターが40くらいのダメージを与えている中、平気で100越えのダメージを与えるようなバランス崩壊キャラとして有名ですね。

中盤以降も耐性の低さなどからきつくなってきても「キラーマシン」や「ユニコーン」への配合先として使えるということでその辺も優秀という。

ただ当時キッズだった僕はそんなこと知らず「グレイトドラゴン」とか見た目のいいキャラ使ってましたね。
大人になってから知りましたが、ドラゴン系はレベルが上がりにくく、耐性も弱めなのが多いので中盤あたりでしんどくなるんですよね。

バトルレックスとかあの辺で結構苦戦してた記憶。
ストロングアニマルの配合例の多さ

本作プレイした人は持っていた人が多いであろうこちらの攻略本。
配合例がすべて載っている素晴らしい本なのですが、ストロングアニマルの欄だけおかしなことになってるんですよね。

なんでこのモンスターだけこんな配合例が多いのかわかりませんが、この攻略本持ってた人はこれが印象に残っている人も多いはず。
テトカス

テト「ひょうがまじん出すからようがんまじん出してくれへん?」
テト:ひょうがまじん×ようがんまじん=ゴールデンゴーレム
テリー:ようがんまじん×ひょうがまじん=ようがんまじん
やっぱりテトカスってクソだわ。
っていうネタですね(笑)

マジレスすると鳥系出すとホークブリザード作れるのでまあ悪くない誘いなんですよね。
マダンテゲー
本編ではミレーユのにじくじゃくが開幕ぶっ放してくることで有名なこの技。


「ぼうぎょ」していないと大事故になるこの技ですが、ガチ対戦でも強い技だったらしく、いつ「マダンテ」撃つかの読みあいゲーになってたようですね。
「だいぼうぎょ」で構えつつ「マダンテ」どこでパナすかという勝負。
耐性があるキャラでも2匹連続で撃たれると終わるため大会での使用は1回までのルールもあったとか。
さすがに強すぎたのか次作のイルルカでは単体攻撃になり弱体化されてしまいましたね。
ミレーユのモンスターのビジュアルの良さ
ミレーユで言うと連れてるモンスターのビジュアルがめちゃくちゃ好きなんですよね。

ラスボスって感じでこの並びすごい好きですね。
ちなみに後のモンスターズシリーズでアホほど聞くことになるこのBGMの初出はミレーユ戦でしたね。
かっこいいBGMですが乱発されすぎで、今ではすっかり安っぽい印象を受けてしまうように。
もっと大事にできなかったかな……
ガチで強いモンスターじいさん

ちなみにモンスターじいさんのモンスターもビジュアルがいいですよね。
これに限らずやっぱりラスボス的な立ち位置のものはビジュアル大事にしてほしいですよね。
ゾーマがシリーズで人気のラスボスなのもビジュアルの良さは影響しているかと。

正直ラプソーンとかねぇ……(笑)
モンスターじいさんの強さの話になりますが、これがまあ強いという。
完全初見で勝った人はいないのではと思えるほどの強さで、対策が必須となりますね。
行動を自分で選べるとまだ楽になるはずですが、AI戦闘なのも難易度を上げているんですよね。

まず「ザオリク」と「ベホマラー」を覚えているゴールデンスライムを倒せないとお話にならないのがきついところ。
「さそうおどり」があるとゴールデンスライムを高い確率で行動不能にできるのであとはアタッカーの攻撃力を高めれば突破口が見えてくるという感じですね。
しかし当時キッズの僕は攻撃系か回復の技しか覚えさせていなかったので全然倒せなかったですね(笑)

ちなみに3DS版では枠の問題で「ローズバトラー」がハブられることに(笑)
フィールドBGMが眠くなる
個人的に過去一で寝落ちしたゲーム。
その原因がこのフィールドのBGMかと。
このBGMなんかすごい催眠効果があったんですよね。
ネットではあまり語られていないような気もしますが同じような人いたんですかね?

フィールドも基本的に似たような絵面が続く影響もあって眠くなるんですかね。
逆輸入キャラの登場
本作発売時点でのナンバリング最新作は『6』でした。

本作の2年後に新作として『7』が出ますが、その『7』に本作オリジナルキャラが逆輸入されるといった影響を与えています。

「にじくじゃく」「ローズバトラー」「ゴールデンスライム」がナンバリング進出を果たしており、以降の人気モンスターとなっています。
『7』は「にじくじゃく」の色違いである「れんごくまちょう」が場違いな所に出てきてヤバい強さだったのは覚えていますね。
ダークドレアムと戦えた没データ
有名な話ですが、データ上では99階層のたびのとびらがあり、奥まで行くとダークドレアムがボスとして出てくるグレイス城の没データがあったようです。


99階層がさすがに長すぎたと判断したのかわかりませんが、どうせなら正規データとして残してほしかったですね。
ゲームボーイカラーに初めて対応したソフト
本作はちょうどゲームボーイカラー本体が発売された時期での発売の作品となっています。
そして初めてゲームボーイカラーに対応したソフトとなっています。

そういった背景もあり、パッケージとソフトに違いがあり、ソフトの色は灰色と黒色になっています。
基本的にモノクロとカラー両方に対応しているGBソフトは黒色のガワ(右側)が使われるようになっていますが、本作の初期盤はゲームボーイカラーが発売される前に発売されたのでソフトが灰色のガワ(左側)になっているみたいですね。

レトロフリークに取り込んでも別のROM扱いになるのでなにかしらバグやら調整が入っているのかも。
レトロフリークでプレイするとフリーズ多発
ゲームの内容と関係ないですが、本作はレトロフリークでプレイするとフリーズが多発します。
特に、
- 配合時にモンスターを選んでいるとき
- たびのとびらで画面が切り替わるとき
がフリーズしやすいですね。

こんな感じです。

そういったことからストレスフリーでプレイするなら実機かSwitchのテリワンレトロのほうがいいかもしれませんね。
テリワンレトロではGB版と違いがあり、
- テリーの歩く速度がアップ
- マップの常時表示
- 仲間ステータス表示
といった機能が追加されています。
GB版では若干ストレスになっていた移動速度ですが、レトロ版では速くなっているのはいいですね。


またマップや仲間のステータスと作戦が画面端に表示され、痒いところに手が届く仕様になっています。
今プレイするならこちらのほうが良さそうですね。
|
ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO|オンラインコード版 |
|
 |
 |
以上になります。
こうして振り返ると話せることがたくさんありましたね。
モンスターズシリーズは今後も続いていくと思いますのでしっかり追い続けていきたいと思います。
 |
 |
 |
|
 |